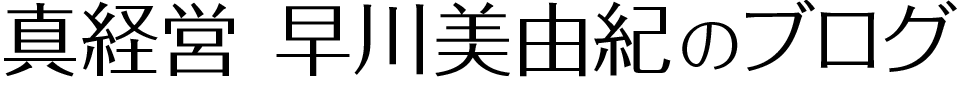先日、野中郁次郎 一橋大学名誉教授がお亡くなりになりました。
修士2年の身である私は、
偶然、野中氏の「SECIモデル」を用いて、
修士論文を執筆していました。
そして、学位取得のかかった口述試験をドキドキのうちに終え、
その翌日の訃報。
一方的にですが、とても寂しく、
2月は野中本月間になりそうです。。。
「書く」という作業は、
自分の無知を受け入れながら、
点と点を結んで線や面にしていく作業。
「SECIモデル」は有名な普遍的理論であり、
知ってはいましたが、
とんだ知っている「つもり」に気づきました。
修士論文を書き終えて、やっと1本線がつながったかなあと。
口述試験を通して、先生から、
「この論文は更に〇〇にも、△△にもつながりそうですね」という
フィードバックをいただきました。
〇〇や△△自体は知っている理論や事象ですが、
きゃ~全然意味わからない(つながりや可能性が自分には全然見えない)!
卒業までに聞いておこう。。。←独り言
「学ぶ」ということは、
まだ見えないものを見ようとすること。
同じものを見ても、同じ文章を読んでも、
人それぞれ違う世界を見ているんだなと改めて実感しました。
ところで、アメリカをはじめ、
経済格差(所得格差)がもとで人々の間に分断が起きています。
分断とは同じ時代を生きていても違う世界を見ていること。
「SECIモデル」では、一人ひとりの知を見える化し、
それを連結することで新たな「組織」の知が創られ、
それを一人ひとりが取り込むことで、
一人ひとりの知もブラッシュアップされるとしています。
そして、そのためには「場」が必要であるとしています。
「組織」を国や全世界と置き換えてみると、
今や、異なる知(世界観や意見)を持つ人達が
同じ「場」に立とうとさえしなくなっているのではないでしょうか。
昔と比べて、SNSという
便利な「場」のインフラも生まれているにも関わらず。
どれだけ感情的なアレルギーが、互いを分かり合えなくし、
まだ見えぬ新たな可能性を潰してしまうことか・・・
と感じています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
◆ドラムサークルを取り入れた内定者研修
「音楽の力」で同期のチームワークを育み、
内定辞退を防ぐ!
https://makoto-mg.co.jp/blog/?p=187
『ドンドコちゃんねる』 でインタビューいただきました。
是非ご登録どうぞ!
https://www.youtube.com/watch?v=v6S7zXiqjMM